昼食の時間が終わる頃、下島八重子さん(仮名)の食事の様子を扉越しにじっと眺めている娘さん(侚子さん:仮名)の姿がありました。
八重子さんの食事を食べる姿はとてもワイルドです。
スプーンを逆手に持って、刻み食をガツガツと口に運びます。そして、極めつけは、必ずお皿をなめ回します。
そして、隣の利用者の食事に手を伸ばし、手づかみで食べようとします。
侚子さんは、美人で上品だった昔の母の姿からは想像できなくて悲しくなると言います。
「どんどん壊れていく母の姿を見ていると何もしてあげられない自分に腹が立つと同時に、母の気持ちを考えると辛くて苦しくなる」と言います。
![]()
八重子さんは、元看護師でした。勤務先の病院で知り合った医師(義明さん:仮名)と結婚して専業主婦となり、娘さんの侚子さんを授かりました。
義明さんとの結婚は、義明さんの両親の大反対を押し切っての結婚だったので、婚家からの風当たりはかなり強かったと言います。
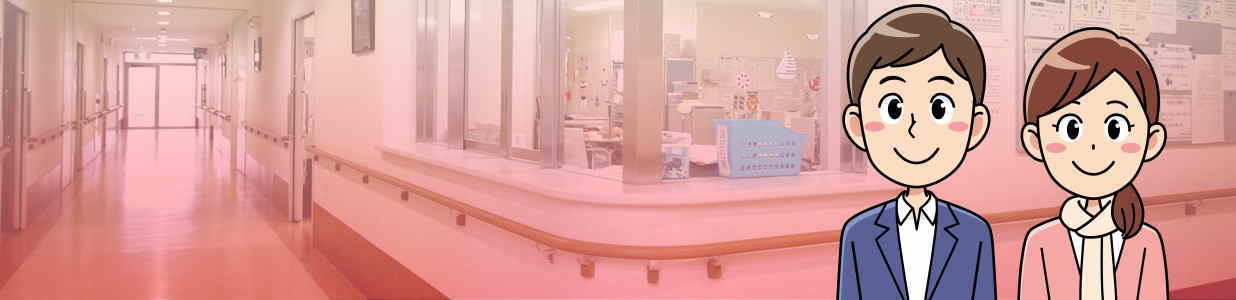
八重子さんは、看護の専門学校を卒業した看護師であり、大学卒業の才女を嫁に欲しかったと言われたそうです。
侚子さんは、大学に進学することも考えましたが、義明さんは、「目的がないのに大学へ行っても意味がないから・・・」と言ってくれたと言います。
義理の両親との関係は、侚子さんを授かってからも変わらなかったと言います。
また、侚子さん以外に子宝に恵まれなかったことも関係を悪くしたのかも知れません。
当時は、医師の子供は医師にする時代。
下島家も代々医師家系で、義明さんの父も兄も医師でした。
義明さんは、そんな侚子さんを気遣っては、親の経営する病院には戻ることなく、生涯、病院の勤務医を続けたと言います。
そんなこともあってか、八重子さんと侚子さんは一卵性の親子の様でした。
容姿も似ているので、「姉妹に見間違えられたのよ!」といって侚子さんは大学時代を振り返っていました。
八重子さんは、一人娘の侚子さんに英才教育を身に着けようと、幼いころから、ピアノやバイオリン、バレエ等を習わせたと言います。
八重子さんも一緒にピアノを習い、一緒に家で弾くこともあったと言います。
そんな侚子さんは東京の音大へ進学、そのまま東京で音楽活動をする中で、同じ音楽関係の方と結婚しました。
東京へ嫁ぐと言った侚子さんの事を、八重子さんは、優しく送り出してくれたと言いますが、心の中では淋しかったのではないかと振り返っておいででした。
侚子さんが嫁いでから、義明さんと八重子さんの二人暮らしがスタートしました。
義明さんは仕事に忙しく、八重子さんは、趣味となったピアノや鼓、ガーデニングを楽しんでいたと言います。

孫が出来てからは、東京へ遊びに来ることも多くなり、学会で出掛ける義明さんに一緒に付いて行くこともあったと言います。
そんな八重子さんの異変に気づいたのは約10年前の70歳位の頃でした。
義明さんは、70歳まで現役で医師として働いていましたが、家庭の事は八重子さんに任せており、家のことは全く分からない状態でした。
義明さんが現役を引退し、八重子さんと二人で過ごすことが多くなりました。そんな時、八重子さんの異変に気づいた義明さんが侚子さんに連絡してきたのです。
その頃になると、八重子さんの外出する機会も減って、侚子さんも実家へ戻ることも少なくなっていました。
連絡をもらった侚子さんは、孫と一緒に実家へ訪問しました。
実家へ訪問した侚子さんは、まず、散らかりっぱなしの部屋に驚きます。
きれい好きな八重子さんの部屋とは思えなかったと言います。
そして、出迎えた八重子さんが、孫に向かって「誰だ!お前は誰だ!」と叫んだと言います。
八重子さんは孫たちが分からなかったのです。想像以上に認知症が進行していました。
しばらく侚子さんは八重子さんと過ごすことにしました。
八重子さんを精神科へ受診させ、内服薬が開始となりましたが、認知症の進行は止めることは出来ません。
侚子さんは、東京都と実家を行き来し、デイサービスやショートステイ、訪問介護などのを最大限活用しながら両親の面倒を見ていましたが、義明さんの入院が重なり、侚子さん自身の疲労も重なって、在宅生活が難しくなりました。
物忘れが激しいと気づいてから5年・・・八重子さんは75歳で特別養護老人ホームへの入所となりました。
入所後に夫である義明さんが病死し、侚子さんが義明さんの死を伝えましたが、表情が変わることはなかったと言います。

現在、八重子さんは、侚子さんをも理解できなくなっています。
侚子さんが声を掛けても怪訝な顔をし、会話も出来なくなりました。
人前で突然、服を脱ぎ棄ててしまうこともしばしば見かけます。
介護拒否も激しく、易怒性が増し、機嫌を損なうと手が付けられなくなることも多く、機嫌が良いタイミングを見計らって援助をしています。
認知症は、その症状の進行に関して明確な方向性が未解明であると言わざるをえません。これが、認知症の証であるということは、外見やその行動、言動の状態だけでは判別できないのが現実です。しかし、明確にある程度わかっているのは、認知症患者の行動は、徐々にその範囲が狭まるということです。
認知症の可能性のある方が家族に存在するときは、異常な行動をすぐに指摘し、否定をもって接しては逆効果になります。
高齢者自身が自覚をもって病院に受診することは皆無だと考えてよいでしょう。また、受診できたとして認知症の初期症状と診断された時には、家族で話し合い、その障害を克服するよう、認知症を受け入れる準備が肝心となります。
認知症は病気だから出来なくなるのは当たり前と諦めるのではなく、出来ないことの手助けをしながら、認知症本人の自信を回復させることがまず先決なのです。そのため、家族は相談相手となり、低下していく行動や認知に対して、本人の自立を促すことが必要となります。


