今日は、以前ご紹介させて頂いた浅子さんの命日です。
享年99歳・・・大往生でした。

入所して5年目のお正月が過ぎた頃、朝のカンファレンスで浅子さんの看取りについての議題が上がりました。
カンファレンス出席者は、生活相談員、介護支援専門員、管理栄養士、介護職員、看護師です。

浅子さんの看取りについて、各部署からの意見を頂きたいと思います。
入所時の意向調査では、浅子さん自身の強い希望もあって、施設の看取りを希望されています。
また、ご家族の方々も浅子さんの意向に添った形でお願いしたいとのことです。
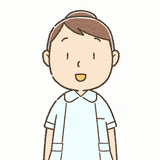
食事摂取が困難となり、血圧も低くなり、発熱もあり、末梢にチアノーゼを認めます。
入所時に施設内での看取りの意向があった方なので、昨日、医師の診察を受けました。
医師の方からも施設内の看取りについて家族に最終的な確認をするよう指示がありました。

食事以外に高カロリーのゼリーやポカリゼリーなどを提供していますが、食事は殆ど摂取できず、十分な栄養管理が難しくなってきました。
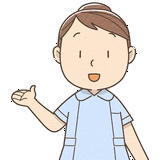
食事摂取量が徐々に減っており、ここ数日間は、重湯を1口しか食べられず、高カロリーゼリーも2口、3口程度しか摂取できていません。
ポカリゼリーやお茶ゼリー等で水分摂取を促していますが、目標の水分が摂取出来ていません。
また、発熱もあり、入浴が中止になっているため、全身清拭を毎日行い、清潔保持に努めています。
着衣もガーゼ時の寝巻に代えて、浅子さんの安楽保持に努めています。

昨日、ご家族が浅子さんと面会され、最終確認を行ったうえで、施設での看取り指針を再度説明し、同意を頂きました。
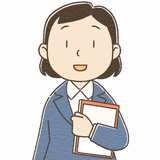
昨夕、ご家族の方々に集まって頂き、最終的に看取りの確認が取れましたので、施設ターミナルケアプランの起案書を作成いたします。
施設長までの決済が終わりましたら、看取り援助マニュアルに沿っての援助に切り替わります。
各部署への周知徹底をお願いします。
特別養護老人ホームでの終末期とは、全身状態が著しく衰弱し、格別の治療方針を立てることもなく、死を迎えるほかない状態を言います。
終末期と考えるためには、ある疾病が発症して、それが原因で著しく衰弱をきたす場合と、特にこれといった症状もないのに食欲がなくなり急速に衰弱が現れる場合とがあります。
勿論、後者の場合、高度な医療を受ければ病名が明瞭になることもありますが、高齢者の場合、特に、90歳を超えるような年齢になると、そこまでの検査を受けるかどうかはケース・バイ・ケースです。
特別養護老人ホームに入所中といえども、治療対象の病気は、外来あるいは入院で治療します。
しかし、これといった病名も付かず、たとえば、病名が明らかになったとしても治療の見込みが立たない場合は、終末期となります。
終末期であっても疼痛があったり、本人の強い希望があったり、家族の要請があったりした場合には入院となるケースがあります。
逆に、本人が治療と入院を断って、家族も特に入院治療を希望しない場合には施設内で死を迎えることになり、ターミナルの開始となります。
※看取りにつきましては下記ページもご覧いただけましたら幸いです。
『看取り指針』

『看取り(ターミナルケア・終末期ケア)に関する理念と実際』

浅子さんは、二人の娘さんに見守られながら息を引き取りました。
安らかな表情でした。
娘さんと一緒に死化粧をしました。
唇にほんのりと紅を差しました。
私が初めて浅子さんに会った頃のような、凛とした浅子さんになりました。
浅子さんの遺品を整理していると、居室の引き出しから一冊のノートが見つかりました。
脳梗塞で右片麻痺となった浅子さんが不自由な左手で書き綴った短歌でした。
『 あなたへと 伝えておきたい ありがとう ずっと一緒に いてくれたこと 』
人は自らの最期をどこで迎えるべきか、という問いに対し、普遍的な答えを用意することは不可能でしょう。また、本人の決定を尊重するといっても、その人が本当に息途絶える瞬間の気持ちは誰にも分かりません。つまり、人の最後の迎え方は千差万別であり、それは本人のそれまでの生き方によって決定されるべきと考えます。

ターミナルケアの本質は、医療行為(延命的処置)をすべきとか、どこまで望むかではなく、人の終焉を「どこで」「誰と」「どのように」迎えるかであると考えます。「独り」もしくは「諸機器だけの中」で息途絶えるのはあまりにも寂しいことです。少なくとも施設ターミナルの本質はそこにあります。
死に場所を自ら選択し、告げる人もいます。入所と同時に終末まで委ねることを明言したり、自分の体力低下を意識し死を予見したところで選択するなど、施設での看取りを希望して、折にふれ言葉にして、周囲にアクションを起こされます。このとき、利用者の心の中では、生活共同体として、看護・介護職員に身を預ける気持ちが起こっているからだと考えています。その期待に応えることは看護・介護冥利に尽きると言えるでしょう。
![]()
死に向き合う介護の存在意義
①長期介護の延長線上に『死』がある
利用者も家族も、施設職員も、ここでは生活共同体としての生活環境をつくってきています。生活全体を支えるというケアする側(家族も含めて)の考え、生活を支えられているという利用者の想いのなかで、長い期間の介護関係が成立しています。施設ターミナルのあり方は、職員の死生観を育み、一人ひとりの考えを生み出していきます。
②高齢者の死と積極的に向き合うことは、死生観を育て次のケアに生きる土壌となる
介護するものにとっては、自分が体験することが不可能な『死』に対峙することで「生きるありよう」を客観的に学ぶことが出来ます。人が、その人生を「良い人生」「良い老後」と評価するとき、その終焉のあり方も重要になってきます。
③終末期にある高齢者に対してすべきことは何かを理解する。
死を受け入れようとしている人の安心感を創造することは、ケアする者が命の価値観、人生観、死生観をしっかりと持ち援助していくことが重要です。施設ターミナルは、①延命するのか、②心に安らぎを与えるか、常日頃から連携をとっておく必要があります。また、施設では、その選択を誰がいつどのように判断し、決定するかです。延命においては本人、家族のニーズと施設の考え方、医師の意見を調整し、判断、入院となります。
④家族への支援
家族介護力に課題を抱え、施設利用を余儀なくされた家族の心情を真に理解することから、家族との円滑な連携が始まります。家族には、過去の経験の有無に関係なく、死の受け入れは慣れないものであり、戸惑うものです。施設ターミナルには、利用者と家族との絆の終わりを太いパイプでつなぐ役割があり、利用者が最後の息一つに安らかさを感じることが出来れば、残された者の心にも光が差し、心から安堵できるものです。
⑤死後の処置
ターミナルケアでは、最後の見届けのあり方と合わせて、エンゼルケア(死後の処置)があります。利用者が一生の仕事を終え、来世に旅立つ身支度として、生前と同じような語り掛けをしながら身体を清めます。身支度においては、生前、お元気なときのお顔に近い状態にすることです。死後、通夜に訪れた、久しぶりに出会う家族・親族・知人等が、故人の安らかな姿に安堵できるよう気を配ります。また、希望されている家族には参加を促し、故人への想いを抱いて死化粧の役割を果たしていただきます。


